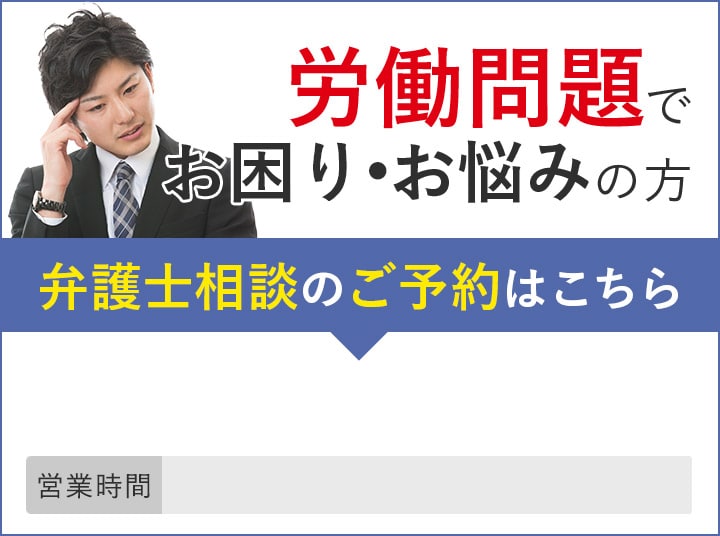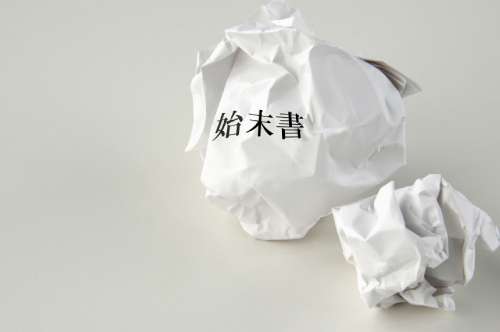転職したら面接時と話が違う! 辞めることはできる? 対処法は?
- 労働条件・ハラスメント
- 転職
- 話が違う
- 辞める

神奈川県労働局が公表している「令和5年度 個別労働紛争解決制度の施行状況等」によると、民事上の個別労働紛争相談件数は、2万181件あり、そのうち「募集・採用」に関する相談は、174件(0.9%)ありました。
たとえば、前職よりも給料や待遇が好条件であったため転職したにもかかわらず、実際には話が違うというケースがあります。このような場合には、話が違うことを理由に辞めることができるのでしょうか。
今回は、転職したら面接時と話が違う場合の対処法や相談先などについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。


1、転職したら話が違うと思った場合に最初にやるべきこと
転職したら話が違うと思った場合、まずは以下のような対応を検討しましょう。
-
(1)労働条件通知書を確認する
労働条件通知書とは、企業が労働者を採用する際に、労働条件などを明示するために労働者に対して交付する書類です。労働基準法では、労働契約締結の際に労働条件の明示が義務付けられていますので、採用時には必ず交付される書面になります(労働基準法15条1項)。
実際に転職してみたら面接時と話が違うと思ったときは、まずは会社から交付された労働条件通知書を確認してみましょう。労働条件通知書に記載された労働条件と実際の労働条件が異なる場合には、直ちに労働契約を解除して退職することが可能です(労働基準法15条2項)。
なお、求人広告や求人票と実際の労働条件が違うだけでは直ちに違法とはいえません。なぜなら、求人票の労働条件は、入社後の労働条件の目安に過ぎず、確定した労働条件ではないからです。 -
(2)会社と話し合う
労働条件通知書に記載された労働条件と実際の労働条件が違っている場合には、まずは会社との話し合いを行いましょう。いきおいで会社を辞めても生活が苦しくなるおそれもあるため、会社を辞めるのは最終手段です。
会社との話し合いで労働条件の見直しに応じてもらえれば、退職することなく、仕事を続けることができる可能性も高まります。労働条件通知書などを提示しながら、話が違うことを伝えて、労働条件の見直しを求めていきましょう。
2、会社に取り合ってもらえない場合の外部相談先
会社が労働条件の見直しに応じてくれないときには、以下のような外部の相談先を利用してみましょう。
-
(1)労働基準監督署
労働基準監督署は、企業が労働基準法などの労働関係法令に違反しないよう取り締まりを行う機関です。実際の労働条件が労働条件通知書と相違がある状態は、労働基準法に違反する状態ですので、転職したら面接時と話が違うことに気付いたときは、労働基準監督署に相談することができます。
労働基準監督署では、労働基準法違反が疑われる事案があると会社への立ち入り調査などを実施します。その結果、労働基準法違反が明らかになったときは「助言指導」や「是正勧告」をしてくれますので、それにより違法状態の改善が期待できます。 -
(2)弁護士
労働問題の実績がある弁護士に相談をすれば、問題解決に向けたアドバイスやサポートを得ることができます。また、会社との代理交渉も可能です。
労働基準監督署の助言指導や是正勧告には強制力がありませんので、事業主がそれに従わない場合には、労働者個人で会社と交渉をしていかなければなりません。しかし、弁護士であれば、労働基準監督署とは異なり、労働者の代理人として会社と交渉をすることができますので、労働者自身で対応する必要はありません。
会社との交渉が負担に感じる方は、弁護士に相談をするのがおすすめです。 -
(3)外部に相談するときに準備するもの・相談の流れ
弁護士への相談は、基本的には予約制となっています。事前に法律事務所に連絡をして、相談日時の予約を取る必要があります。事務所によって、対面、電話、オンラインなど多様な方法が選べるため、相談してみましょう。
他方、労働基準監督署は、予約は不要です。面談相談だけでなく、電話での相談やメールでの情報提供も受け付けています。ただし、急を要する場合は、面談での相談がいいでしょう。
相談時間は30~60分など限られていることが多いため、以下のようなものを準備しておくとよいでしょう。- トラブルの経緯を時系列でまとめたメモ
- 労働条件通知書などの関係する証拠
トラブルに関係する証拠が複数あるときはすべて持参するようにしてください。自分では不要だと思った証拠が、実は重要な証拠であることもあります。
お問い合わせください。
3、試用期間で辞めることは可能か
転職したら話が違うという場合、試用期間で辞めることはできるのでしょうか。
-
(1)試用期間とは
試用期間とは、企業が労働者を採用した後、本採用するかどうかを判断するために設けられている期間です。
試用期間の長さは、法律上特別な定めはありませんので、企業が自由に設定することができますが、1か月から6か月程度が一般的です。
試用期間というと「お試し期間」というイメージを持たれる方も多いですが、試用期間であっても会社と労働者との間には労働契約が成立していますので、会社から簡単に解雇されることはありません。 -
(2)試用期間中でも2週間前まで伝えれば退職可能
試用期間中に労働条件の相違など話が違うことに気付いた場合には、退職希望日の2週間前までに申し出をすることで会社を退職することができます。
また、労働条件通知書に記載された労働条件と実際の労働条件との間に相違がある場合には、2週間を待つことなく直ちに会社を辞めることができます。
なお、試用期間中に退職の意思を伝えた場合、会社から「すぐ辞めるなら給料は支払わない」、「損害賠償請求をする」などといわれるケースもあります。しかし、このような対応は基本的には違法となりますので、会社からこのような発言があったときは、2章で説明した外部の相談先に相談をするようにしましょう。
4、辞めさせてもらえない場合の対処法
会社に退職の意思を伝えても、辞めさせてもらえないという場合には、以下のような対処法を検討しましょう。
-
(1)内容証明郵便で退職届を送る
退職の意思表示をしたという証拠を残すためにも、必ず、内容証明郵便を利用して退職の意思表示を行うようにしましょう。後で会社から「退職の意思を伝えられた覚えはない」などと反論される可能性もあるため、証拠となる書面に残すことが大切です。
なお、法律上、労働者から退職の意思表示をしてから2週間経過により、退職の効果が生じます(民法627条)そのため、退職の意思表示は、退職日の2週間前までにするとよいでしょう。
ただし、労働条件通知書に記載された労働条件と実際の労働条件との間に相違がある場合には、2週間を待つことなく直ちに会社を辞めることができます。 -
(2)退職代行を利用する
労働者個人で退職手続を進めるのが不安だという場合には、退職代行という手段もあります。退職代行とは、労働者に代わって退職手続を進めてくれるサービスであり、民間業者や弁護士などに依頼することができます。
民間の退職代行業者は、労働者に代わって退職の意思を表示することができますが、基本的にはそれ以外の対応はできません。
弁護士であれば退職代行だけでなく、以下の対応についても労働者の代理人として行うことができます。- 退職日の調整
- 業務の引き継ぎ
- 有給休暇の消化
- 退職金の金額や支払い方法の調整
- 未払い残業代の請求
5、まとめ
転職したら、面接時の話と違うということは珍しい話ではありません。労働条件や仕事内容の相違に気付いたときは、すぐに労働条件通知書を確認し、実際の労働条件との間に違いがあるかどうかをチェックすることが大切です。
労働条件通知書に記載された内容と実際の労働条件が異なるときは、まずは会社と話し合って労働条件の見直しを求めていくとよいでしょう。労働者個人で対応するのが難しいときは、弁護士に交渉を依頼するのもおすすめです。まずはベリーベスト法律事務所 小田原オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|