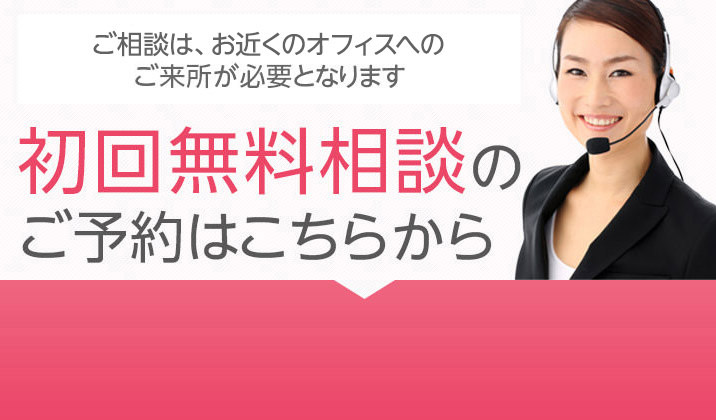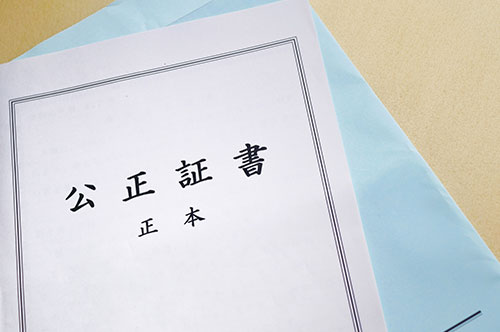養育費を支払わない人にペナルティーはある? 未払い時の対処法
- 養育費
- 養育費
- ペナルティ

小田原市が発表している統計要覧によると、小田原市の令和4年度の離婚件数は258件となっています。
子どもがいる夫婦の多くは、離婚時にする際に公正証書や調停などで養育費の取り決めをしますが、残念ながら離婚後、取り決め通りに支払われないケースは少なくありません。
では養育費を支払わない相手には何かペナルティーがあるのでしょうか? また未払い養育費を回収するためにはどうすればいいのでしょうか? ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説していきます。


1、養育費の未払いにペナルティーはある?
養育費を支払わない相手に対するペナルティーについて説明していきます。
-
(1)刑事罰となるペナルティーはない
取り決めていた養育費を支払わないことは犯罪ではありません。したがって、懲役や罰金といったペナルティー、いわゆる刑事罰を受けることはないのです。
しかし、刑事罰に当たらないからといって何のペナルティーも科されないというわけではありません。 -
(2)未払い分には遅延損害金が科される
未払いに対するペナルティーの1つが「遅延損害金」です。実際に請求することはほとんどありませんが、養育費の支払いは金銭債務であることから、未払い分の養育費の金額に加えて「遅延損害金」を求めることができます。逆にいえば、未払い分に対するペナルティーとして遅延損害金以上の金額を科す(養育費の増額など)ことは難しいため、「遅延損害金」が未払い分に対する唯一の金銭的ペナルティーといえるでしょう。
なお、改正民法施行前の令和2年3月31日までに養育費の取り決めをしていた場合の法定利率は5%ですが、それ以降に取り決めをしていた場合の法定利率は3%です。
ただし、公正証書などで養育費の遅延損害金の利率を決めていれば、法令の制限内である限り、その利率が優先されます。 -
(3)支払われない養育費を強制的に回収することは可能
養育費を支払わない人から、未払いの養育費を強制的に回収できる方法があります。「間接強制」と「強制執行」です。詳しくは次章で解説します。
-
(4)財産開示をしない場合・嘘の陳述をした場合には刑事罰が科される
前述の通り、養育費を支払わなかったからといって、それだけで逮捕されるようなことはありません。しかし、未払い分を回収するための方法である「強制執行」をするには、債務者(支払う義務がある側)の財産情報を特定する必要があります。相手から財産情報を教えてもらえない場合に行う手続きが「財産開示手続」です。
「財産開示手続」は、裁判所が債務者を呼び出して自分の財産情報を陳述させる手続きのことで、この手続きによって債権者(養育費を受け取る側)が債務者の財産の情報を得ることができます。
財産開示手続は、令和2年4月1日の改正民事執行法施行以前は債務者が呼び出しに応じない場合等の制裁が少ないことから債務者が出頭をしないために財産情報を得られず、強制執行を行えないケースが多かったためにあまり意味のない手続きだといわれていました。
しかし、従来であれば財産開示期日に出頭しない場合や嘘の陳述をした場合「30万円以下の過料」が科される行政罰だったところが、改正後は「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科される刑事罰(民事執行法 第213条)となっています。
さらに、金融機関や登記所、自治体など債務者以外の第三者からの情報取得手続きができるという法改正もされたため、財産情報は把握しやすくなっているといえます。
2、養育費を支払わない相手から強制的に回収する方法|強制執行
養育費を支払わない人から裁判所の力を借りて強制的に未払い分を回収するための手続きが「強制執行」です。「強制執行」は、債権者が裁判所に申し立てを行うことで、債務を履行しない債務者に対して、裁判所が強制的に債務を履行させる手続きを指します。中でも給料や預貯金を差し押さえる強制執行を「債権執行」といいます。
「強制執行」には、「間接強制」と「直接強制」の2つの方法があるため、それぞれの内容をみていきましょう。
-
(1)間接強制
「間接強制」とは、債務を履行しない債務者に対して「一定期間内に履行しなければ、債務とは別に制裁としていくらの金銭の支払を命ずる」と警告することで心理的プレッシャーを与え、債務の履行を促す方法です。
間接強制(制裁金を設定することによって履行を促す方法)は従来、子どもとの面会交流のような、直接強制が認められていないケースに利用されていましたが、平成16年の民事執行法改正によって、現在は養育費のような直接強制が認められている場合でも間接強制が認められるようになりました。
間接強制が命じられても、相手方が間接強制金や養育費を支払うとは限りません。したがって、直ちに相手の給料を差し押さえたい場合には向かない方法です。しかし、次に解説する「直接強制」で給料を差し押さえられた債務者が、職場に居づらくなり辞めてしまうことで養育費が支払えなくなってしまう恐れもあります。間接強制はそういったリスクを回避したい場合に有効といえるでしょう。 -
(2)直接強制
「直接強制」は、債務を履行しない債務者に、直接的に債務を履行させる方法です。養育費を支払わない相手に対して直接強制を行うと、相手の給与や預貯金を差し押さえて、強制的に支払い義務を履行させたのと同じ効果を得ることができます。
なお、「強制執行認諾文言付き公正証書(執行証書)」があれば、調停手続を経なくても強制執行手続きができるため、離婚する際の養育費に関する取り決めは公正証書にしておくことがおすすめです。
お問い合わせください。
3、養育費の未払いを防ぐための方法
養育費の未払い分は、前述の通り「強制執行」で回収できますが、できれば未払い自体を事前に防ぎたいものです。そこで、養育費の未払いを防ぐための方法を4つご紹介していきます。
-
(1)公正証書や調停調書を作成しておく
養育費の未払いを防ぐためにも、公証人が作成する公文書である「公正証書」や「調停調書」を作成しておきましょう。未払いの養育費がある場合、強制執行手続きができます。
なお、公正証書や調停調書は離婚後でも作成することができるため、離婚時には離婚協議書を作成するだけにしていた場合は、離婚後にそれを公正証書にしたり、養育費調停を起こすことをおすすめします。 -
(2)適正な範囲の養育費を設定する
養育費の金額は話し合い次第で自由に決められるため、相手が同意すれば高額な養育費を設定することも可能です。しかし、あまり高額な養育費を設定しておくと、後々相手が支払えなくなる可能性があります。
それを防ぐためにも、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に、収入に見合った適正な範囲の養育費を設定するようにしましょう。
ベリーベストでも簡単に養育費の計算ができるシミュレーションツールを用意しています。
また、相手の収入の減少や扶養人数の変化(相手が再婚したなど)により減額を求められた場合(養育費減額調停)は、その相談に応じることも大切です。ただしその際は、相手の要求する通りに応じるのではなく、適正な価格になるように交渉する必要があるでしょう。
-
(3)可能な範囲で面会交流をする
離婚後に、親権を持たない方の親が子どもと定期的に会って話をしたり、電話や手紙などでコミュニケーションをとったりすることを「面会交流」といいます。
可能な範囲で面会交流をすることは、養育費の未払いを防ぐ効果があります。やむを得ない事情(離婚理由が自分へのDVや子どもへの虐待など)がない場合は、なるべく面会交流をさせることで子どもへの親心が育まれ、お金を支払う気持ちを維持することにつながるのです。 -
(4)一度でも未払いが発生したら弁護士から連絡してもらう
未払い状態が続かないように、一度でも未払いが発生したら弁護士から相手に連絡してもらうことも大切です。弁護士が出てくることで相手に本気度が伝わり、真摯(しんし)に対応してもらえる可能性が高まります。
また、弁護士から支払わないことに対するリスク(遅延損害金や強制執行など)を説明してもらえるため、その後に再び未払いが起きることを防ぐ効果があるでしょう。
4、養育費の未払いの対応を弁護士に依頼するメリット
未払い養育費の回収対応は弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士に依頼すると、弁護士名義で内容証明を送れるため相手に本気度が伝わり、心理的プレッシャーを与えて支払いに応じてもらいやすくなります。
また、養育費の取り決めを離婚協議書にしていた場合は、未払い時に強制執行ができないため、養育費請求調停や審判を起こして、改めて養育費についての取り決めを行わなければなりません。
弁護士に依頼をしておくことで、調停や審判の手続きだけでなく、その後の強制執行などの手続きについても任せることができるため、未払いが起きたら早めに弁護士に依頼するようにするといいでしょう。
5、まとめ
養育費の請求は、子どものための正当な権利です。養育費の未払いに対しては、「遅延損害金」や「強制執行」といったペナルティーで支払いを促すことができますが、事前に未払いが起きないように対策をしておくことが大切です。
具体的には公正証書の作成や適正な金額での養育費の設定などが有効です。弁護士に依頼すると、それらに関するサポートを受けることが可能な上、未払い時の対応も任せることができます。
養育費の未払いでお困りの際は、ぜひベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています