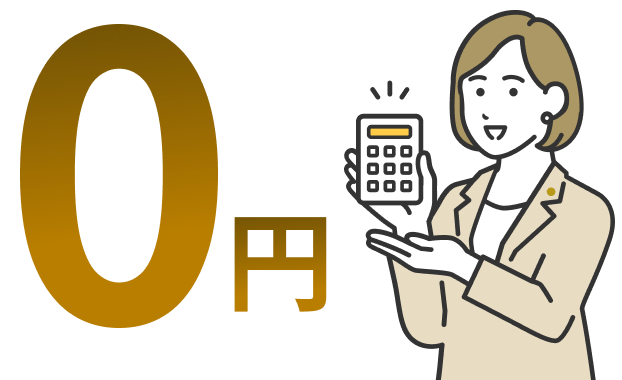親のマンションを遺産相続するときの手続きと注意点を弁護士が解説
- 遺産を受け取る方
- 遺産相続
- マンション

小田原市の統計によると、市民相談室における令和4年度の相続問題相談件数は578件でした。令和2年度は409件、令和3年度は476件となっており、相続に関する相談件数は年々増加しています。
親の財産であるマンションを相続することになり、どうすればいいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。相続財産の中でも不動産は金額が大きく、相続手続きが複雑化しやすいため、慎重に対応する必要があります。
本コラムでは、マンションの相続手続きや相続する際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和5年版小田原市統計要覧」(小田原市)


1、相続時の選択肢は3つ
相続方法には単純承認・相続放棄・限定承認の3つの方法があります。それぞれどのような相続方法なのかを理解し、自身の状況に合った方法を選択しましょう。
-
(1)単純承認
単純承認とは、亡くなった人の財産をすべて相続する相続方法です。
相続財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も含まれます。プラスの財産もマイナスの財産も含めてそのまま相続してもよい場合は、単純承認を選択しましょう。
熟慮期間内に相続放棄や限定承認の手続きをしなかった場合は、自動的に単純承認をしたことになります。熟慮期間とは、相続が開始し、自身が相続人であると知ったときから3か月の期間を指します。
なお、3か月経過する前に相続財産を処分したり消費したりすると、その時点で単純承認を選んだとみなされるため注意が必要です。 -
(2)相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続せずに放棄する方法です。プラスの財産(預貯金など)よりも借金やローンが多い場合や、財産を管理する余裕がない場合などに選択します。
相続放棄を選択する場合は、相続開始を知ったときから3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。
相続放棄は相続権を全て放棄する選択であるため、相続したい財産がある場合には単純承認もしくは限定承認を選びましょう。 -
(3)限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する相続方法です。プラスとマイナスどちらの財産が多いのかわからない場合や、借金があるものの手放したくない財産がある場合などに選択します。
限定承認を選択する際は、相続開始を知ったときから3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。
相続放棄は相続人個人の判断で申し立てできますが、限定承認の申し立ては相続人全員で行わなければなりません。手続きが複雑で時間がかかるケースも多いため、限定承認を選びたい場合には弁護士へ相談するのをおすすめします。
2、親のマンションを遺産相続するときの手続きの流れ
親のマンションを相続する際は、いくつかの手続きが必要です。以下では、一般的な手続きの流れを解説します。
-
(1)遺言書の有無を確認する
相続が始まったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書は、本人の自筆で作成し保管されているケースのほか、公証役場や法務局で保管されているケースもあります。自宅で発見した場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となるため、その場で開封しないよう注意してください。
有効な遺言書が残されていた場合、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めていく必要があります。 -
(2)法定相続人と相続財産を調査する
遺言書確認の次に行うのは、法定相続人および相続財産の調査です。法定相続人とは、法律で決められた、遺産を相続する権利をもつ人を指します。
法定相続人を調査する際は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して確認しましょう。
また、相続人の調査と並行して、預貯金・不動産・株・借金などの相続財産の調査も重要です。
マンションなどの不動産は、毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。固定資産税の納税通知書とは、物件ごとの固定資産税評価額や課税内容が記載された書面です。
納税通知書で確認できない場合は、不動産の一覧表である「名寄帳」を市区町村の役所で取り寄せて確認しましょう。 -
(3)相続人全員が参加する遺産分割協議を行う
遺言書が残されていない場合や、遺言以外の方法で相続を進める場合は、相続人全員が参加する遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続財産の分割方法や割合について相続人間で話し合う手続きです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人がひとりでも欠けた状態で遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となってしまうため注意しましょう。
全員の合意が得られたら、合意に至った内容を記載した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、その後の相続手続きで必要となる可能性があるため作成しておくのがおすすめです。 -
(4)相続登記の手続きをする
マンションを取得する相続人が決まったら、相続登記(名義変更)の申請手続きを行いましょう。
相続登記は不動産の所有権の取得を知った日、もしくは遺産分割が成立した日から3年以内に行わなければなりません。
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となるため注意が必要です。また、マンションの相続登記をしなければ、売却できないなどの権利上の不都合も生じます。
もし期限内の手続きが難しい場合は、「相続人申告登記」を利用することで簡易的な申請が可能です。相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなり、自身が相続人になったと申し出ることで登記義務を果たしたものとみなす制度です。
相続人申告登記を行えば期限超過による過料を回避できるため、期限に間に合わない場合は検討してみてください。 -
(5)相続税の申告と納付を行う
相続財産の総額が一定額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。
相続税申告と納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。正当な理由なく申告・納付をしなかった場合、延滞税や加算税などのペナルティーが課される可能性もあるため注意してください。
なお、相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は課税されないため申告は不要です。相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税を計算する際はまず上記の計算式で基礎控除額を算出し、申告が必要かどうかを判断しましょう。
お問い合わせください。
3、親のマンションを相続した後の活用方法と注意点
親のマンションを相続した後は、どのように活用すればいいのでしょうか? 3つの活用方法とともに、それぞれの注意点について解説します。
-
(1)相続人が住む
相続したマンションの活用方法のひとつとして、相続人自身が住むという選択があります。
住む場所を必要としている場合や、愛着のある住居を引き継ぎたい場合などに適した方法です。賃貸から引っ越す場合は家賃を支払う必要がなくなるため、固定費の負担を抑えられるメリットがあります。
しかし、住居として活用する場合でも管理費や固定資産税といったコストは発生します。引っ越しを考える際には、マンションの状態や維持費用を事前に確認し、長期的な計画を立てることが大切です。 -
(2)売却して現金化する
相続したマンションを売却し、現金化するのもひとつの手段です。
売却すれば維持費や固定資産税の負担がなくなり、売却によって得た現金を新たな投資や必要な支出に回せます。
ただし、売却する際には仲介手数料や印紙税・譲渡所得税などの費用を支払う必要がある点に注意しましょう。マンションの築年数が経過していたり老朽化が進んでいたりする場合は、希望する価格で売却できない可能性もあります。 -
(3)賃貸物件として貸し出す
相続したマンションを賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る方法も有効です。
入居者が見つかれば、安定した収入源を確保できます。また、貸し出しをやめた後、自分で住めるメリットもあります。
一方で、空室リスクや管理費用・仲介手数料などの費用が発生する点には注意が必要です。老朽化している場合は入居者が見つからない可能性もあるため、修繕費用やリフォーム費用も考慮した上で検討しましょう。
4、遺産相続のお悩みを弁護士に相談するメリット
マンションを含む遺産相続で悩んだときは、弁護士への相談をおすすめします。弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。
-
(1)弁護士であれば、評価方法や分割方法のアドバイスができる
弁護士に相談すると、マンションの適切な評価方法や分割方法についてアドバイスを受けられます。
相続財産に不動産が含まれている場合、相続税評価額は遺産分割や相続税に影響する重要な要素となります。不動産は市場価値が変動しやすく、正確に評価するのが難しいため、弁護士の助言を得ることが有効です。
また、不動産には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つの分割方法があり、状況に応じて選択する必要があります。弁護士であれば、適切な分割方法について具体的なアドバイスが可能です。 -
(2)相続人間のトラブルに対応できる
弁護士は、相続人間のトラブルにも対応できます。
遺産相続では、相続人間の意見の食い違いが争いに発展してしまうケースもあります。親族間の話し合いは感情的な対立が起こることもありますが、第三者の弁護士を介することで紛争を回避できる可能性が高まります。
また、弁護士は相続人との連絡や交渉の代行が可能なため、直接話し合うストレスから解放されるのもメリットです。万が一裁判に発展した場合でも、弁護士であれば裁判の代理人となれます。
5、まとめ
親のマンションを相続する際は、相続方法や手続き・相続後の活用方法など、さまざまな要素を考慮する必要があります。
不動産相続には複雑な手続きや法律が絡むため、個人での対応が難しいケースもあるでしょう。
マンションを相続すべきか、またどのように手続きを進めればいいか悩んでいる方は、お早めにベリーベスト法律事務所 小田原オフィスにご相談ください。弁護士が状況に合った最適な解決策をご提案いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています