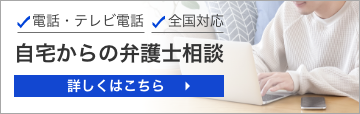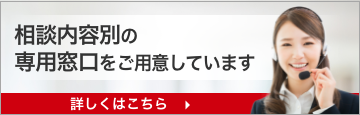就業規則の効力とは? 発生要件や作成する際の注意点を弁護士が解説
- 一般企業法務
- 就業規則
- 効力
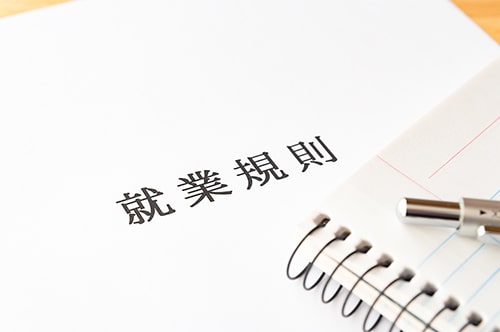
2023年度に神奈川県内の総合労働相談コーナーに寄せられた労働に関する相談は7万5619件でした。
就業規則には、事業場の労働者に共通する労働条件や、労働条件の最低基準を定める効力があります。また、一定の要件を満たす場合に限り、就業規則の変更によって既存の従業員の労働条件を変更することも可能です。
本記事では、就業規則の効力やその発生要件、就業規則を作成する際に必要な手続きや注意点などをベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。
1、就業規則の効力とは?
就業規則とは、労働条件や職場内の規律などを定めた文書です。就業規則には、主に以下のような効力があります。
-
(1)事業場の労働者に共通する労働条件を定める
就業規則は事業場ごとに作成され、その事業場に勤務するすべての労働者に適用されます。
使用者が合理的な労働条件を定めた就業規則を作成し、その就業規則を事業場の労働者に周知させていた場合は、原則としてその労働条件がすべての労働者に対して適用されます(労働契約法第7条本文)。
つまり就業規則には、事業場の労働者に共通する労働条件を定める効力があります。
ただし、労働契約において就業規則の水準を上回る労働条件を定めた場合は、労働契約で定めた労働条件が優先的に適用されます(同条但し書き)。 -
(2)既存の労働者の労働条件を変更する
就業規則における労働条件を労働者の有利に変更した場合、変更後の労働条件が既存の労働者に対しても適用されます。
これに対して、就業規則における労働条件を労働者の不利益に変更しても、原則として既存の労働者の労働条件は変更されません(労働契約法第9条)。
ただし例外的に、以下の要件をすべて満たす場合には、就業規則の変更によって既存の労働者の労働条件を不利益に変更することが可能です(同法第10条)。就業規則の変更による労働条件の不利益変更の要件 ① 変更後の就業規則を労働者に周知させたこと
② 就業規則の変更が、以下の事情に照らして合理的なものであること
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
-
(3)労働条件の最低基準を定める
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となります(労働契約法第12条)。
この場合、無効となった部分については就業規則上の労働条件が適用されます。つまり就業規則には、事業場の労働者に関して、労働条件の最低基準を定める効力があるということです。
2、就業規則の効力の発生要件
前述の就業規則の効力は、それぞれ以下の要件を満たしていることを条件として発生します。
- 当該労働条件が合理的であること
- 使用者が労働者に対して、就業規則を周知させていたこと
② 既存の労働者の労働条件を変更する効力
- 使用者が労働者に対して、就業規則を周知させていたこと
- 当該変更が労働者にとって有利であること、または就業規則の変更による労働条件の不利益変更の要件(前掲)を満たすこと
③ 労働条件の最低基準を定める効力
- 従業員への周知または就業規則の届出
なお、就業規則の周知については、労働基準法施行規則所定の方法によって行う必要がある点にご注意ください(後述)。
お問い合わせください。
3、就業規則を作成する際に必要な手続き・注意点
常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則の作成が義務付けられるとともに、作成に当たって以下の手続きを行う必要があります。
※常時使用する労働者が9人以下の事業場では、就業規則の作成は任意であるほか、以下の手続きは不要です。
-
(1)絶対的必要記載事項を記載する
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則において以下の事項を必ず定めなければなりません(=絶対的必要記載事項)。
絶対的必要記載事項 - 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合は就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
-
(2)相対的必要記載事項を記載する
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、以下の事項を定める場合には、就業規則に記載する必要があります(=相対的記載事項)。
絶対的必要記載事項とは異なり、相対的必要記載事項の定めがない場合は、就業規則にも記載する必要はありません。相対的必要記載事項 - 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
- 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰および制裁に関する事項
- 上記のほか、事業場の全労働者に共通して適用される事項
なお、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項のほかにも、使用者は公序良俗等に反しない範囲内で任意的記載事項を定めることができます。
-
(3)労働者側の意見を聴取する
就業規則を作成または変更する際には、労働者側の意見を聴く必要があります(労働基準法第90条第1項)。
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者から意見を聴取します。
なお、使用者は労働者側の意見を聴く必要があるものの、その意見に従う必要はありません。労働者側の意見を就業規則に反映させるかどうかは、使用者がその裁量によって判断できます。 -
(4)意見書を添付して労働基準監督署に届け出る
常時10人以上の労働者を使用する事業場における就業規則の作成・変更は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条)。
届出に当たっては、労働者側の意見を記した書面を添付しなければなりません(同法第90条第2項)。労働者側に意見書を作成してもらい、交付を受けましょう。
就業規則(変更)届と意見書の様式例は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」(厚生労働省) -
(5)労働者に対して就業規則を周知させる
就業規則を作成または変更した場合には、その内容を労働者に対して周知させなければなりません。周知を怠ると、就業規則の効力が生じないことがあるので注意が必要です。
労働者に対する周知は、以下のいずれかの方法によって行う必要があります(労働基準法第106条第1項、同法施行規則第52条の2)。事業場の状況に合わせて、適切な周知の方法を選択しましょう。- ① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
- ② 書面を労働者に交付する
- ③ 電子ファイル等に記録し、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
- ① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
4、就業規則に関するお悩みは弁護士に相談を
就業規則の作成や変更についてお悩みの企業(会社)は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、企業の実情に合わせた就業規則の内容を検討し、適切な文言によって就業規則の条文を作成いたします。
また、労働者側からの意見聴取・労働基準監督署への届出・労働者への周知など、就業規則の作成・変更に伴い必要となる手続きについても、弁護士が全面的にサポートいたします。
さらに弁護士には、就業規則に関する事柄以外の法律問題についてもご相談が可能です。未払い残業代請求や解雇トラブルなどの労働問題に加えて、契約書のレビュー・契約トラブルへの対応・官公庁対応など、幅広い事柄についてご相談ください。
ベリーベスト法律事務所には、ニーズによってフレキシブルにご相談いただける月額定額制の顧問弁護士サービスがございます。まずは、お気軽にお問い合わせください。
5、まとめ
就業規則には、事業場の労働者に共通する労働条件を定める効力、既存の労働者の労働条件を変更する効力、労働条件の最低基準を定める効力などがあります。
ただし、労働者に対する周知を行うなど、一定の要件を満たさなければ就業規則の効力は生じません。就業規則の取り扱いについて不安がある場合は、弁護士のアドバイスを受けることが有効です。
ベリーベスト法律事務所は、人事・労務管理に関する企業のご相談を随時受け付けております。就業規則の作成や変更などについてお悩みの企業は、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています